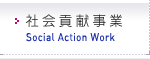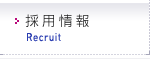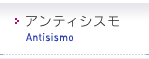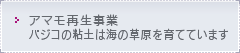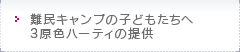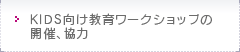写真提供:株式会社東京久栄 PAT.1980023

写真提供:株式会社東京久栄
海の中にも広大な草原「アマモ場」。陸上のイネに似た海草「アマモ」は、今から1億年ほど前に陸から再び海に帰化した植物で、静かな入り江の浅い砂地の海底に生い茂っています。そこは酸素と小さな動植物にあふれ、魚や貝たちにとってはゆりかごのような存在です。
しかし、高度経済成長期の埋め立てや工場・家庭排水による水質の悪化などによって草原の面積は大きく減り、私たちがこれまで食べてきた魚や貝も減少しました。
これを受けて、日本をはじめ世界各国でアマモ場を回復しようとする取り組みが始まりましたが、そこには大きな問題が横たわっていました。浅い海の中は潮や波による流れが絶えず押し寄せすぐに流されてしまうため、アマモの苗を移植したり、種を播くことができなかったのです。かといって、アマモの苗や種に硬く重いものを付けると、根や茎が成長しません。

そこで私たちパジコは、アマモの生長を阻害しない柔らかく重い素材、やがて土に還る自然環境に配慮した素材の開発に取り組みました。それがアマモ用粘土です。
アマモのために生まれたこの粘土は、「重し」の役目を果たすもので、アマモの根元に巻きつけたり、種をまぶして使われます。素材は貝殻やサンゴと同じ炭酸カルシウムを中心とした自然素材からできており、アマモが根付く頃には、とけて海に還ります。

また、誰もが楽しく易しく安全に扱える粘土の使用によって、アマモ場再生活動に児童や市民の参加が可能となりました。
1991年に始まったアマモ用粘土によるアマモ場の修復や再生活動は、東京湾や瀬戸内海、九州・沖縄地方、そして韓国や北アフリカなど、世界各地にひろがっています。これまでに直接修復・再生したアマモ場の面積は約5ヘクタール、東京ドーム1個分に達しています。